生理中の黒い血は病気のサイン?ホルモンバランスや疾患との関係
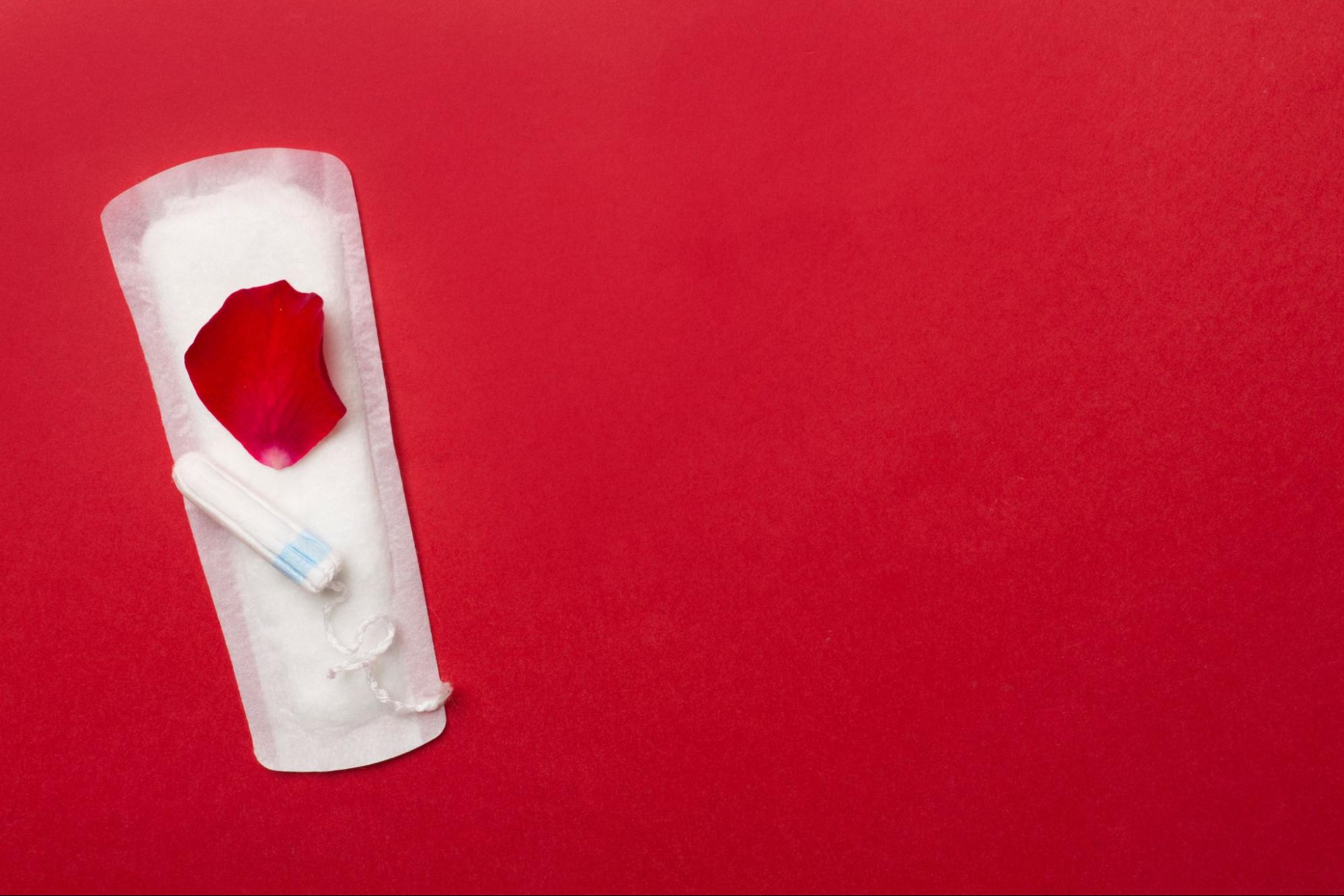
生理中に黒っぽい経血が見られると、驚いたり不安を感じたりする方も多いのではないでしょうか。
黒い経血は、酸化やホルモンバランスの乱れによる自然な現象である場合がほとんどですが、時には婦人科系疾患のサインである可能性もあります。
この記事では、黒い経血が発生する原因や考えられる病気、そしてセルフケアから医療機関での治療まで、具体的な対処法を詳しく解説します。
生理中の経血の色とは?黒い血が出る理由

経血は単なる血液ではなく、子宮内膜や粘液、細菌などが混ざった複合的な体液です。そのため、通常の血液とは異なる性質を持っています。
経血の色は生理周期や状態によって変化し、通常は鮮やかな赤色から暗赤色、茶褐色へと移行し、生理後半になるほど酸化が進むため色が濃くなることがあります。
特に排出まで時間がかかる場合や、生理後半に見られやすいです。
黒っぽい色になる場合もあり、これは経血が子宮や膣内に長時間留まり、酸化した結果です。多くの場合、正常範囲内ですが、異常を感じた場合は婦人科で相談しましょう。
黒い血が示す注意すべきサイン

黒い経血は、通常の生理現象として酸化による色の変化である場合が多いですが、時には体調や婦人科系疾患のサインである可能性もあります。
ここでは、黒い経血が示す注意すべきサインを解説します。
生理期間外で黒っぽい出血が続く
生理期間外に黒っぽい出血が続く場合、不正出血の可能性が考えられます。
不正出血は、ホルモンバランスの乱れや子宮筋腫、子宮頸がん・子宮体がんなどの病気が原因となることが多いです。
また、ストレスや過度な疲労によってホルモンが乱れることでも引き起こされるケースがあります。
特に閉経後にこのような症状が見られるときは、早急に医療機関で診察を受けることが重要です。
1週間以上黒っぽい経血がダラダラと排出される
通常の生理期間は3〜7日程度ですが、それを超えて黒っぽい経血がダラダラと続く場合、子宮内膜症や子宮腺筋症などの病気と関連している可能性があります。
また、経血量が極端に多い場合や強い生理痛を伴う場合は、過多月経や子宮筋腫などの疾患が疑われます。
長引く生理は貧血や体力低下にもつながるため、早めに受診しましょう。
黒い血に強い臭いや腹痛を伴う
黒い血に強い臭いや腹痛が見られる場合、感染症や炎症が原因である可能性が高いです。
具体的には、子宮内感染症や膣炎などが関与していることがあり、これらは放置すると症状が悪化する恐れがあります。
異臭は細菌の増殖や膣内環境の乱れによるものと考えられます。
また、妊娠中にこのような症状が現れる場合は、流産や子宮外妊娠といった深刻な問題に発展する可能性も否定できません。
特に強い腹痛を伴う場合は緊急性が高いため、速やかに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。自分の体調の変化を見逃さず、早めの対応を心掛けましょう。
黒い経血に関連する疾患

黒い経血は多くの場合、酸化による自然な変化ですが、時には婦人科系疾患のサインである可能性があります。ここでは、黒い経血と関連する主な疾患について解説します。
子宮筋腫
子宮筋腫は、子宮の筋肉(平滑筋)にできる良性の腫瘍で、婦人科疾患の中で最も頻度が高い病気です。
進行すると、不正出血や月経過多を引き起こし、子宮内に血液が溜まった結果、排出されるまでに時間がかかり、黒っぽい経血として現れることがあります。
筋腫はその発生部位や大きさ、数によって症状が異なり、無症状の場合もあれば、日常生活に支障をきたすほどの症状を引き起こすこともあります。
子宮筋腫は発生する部位によって以下の3つに分類されます。
- 粘膜下筋腫
- 筋層内筋腫
- 漿膜下(しょうまくか)筋腫
子宮筋腫は良性疾患ですが、その大きさや位置によって日常生活に支障を来す場合があります。
特に過多月経や不妊など深刻な症状がある場合は早めに医療機関で相談し、自分に合った治療法を選択しましょう。
子宮頸がん
子宮頸がんは、子宮の入口(頸部)に発生するがんで、初期段階では症状が現れにくいことが特徴です。
しかし、進行すると不正出血やおりものの異常が現れることがあります。
茶色や黒っぽいおりものは、血液が混ざり酸化した結果である可能性が高く、進行に伴いおりものの量が増えたり異臭を伴ったりする場合もあります。
通常の生理とは異なるこれらの症状には注意が必要です。
主な原因としてヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が挙げられ、性交経験のある女性なら誰でも発症リスクを持つとされています。
特に閉経後の出血や性交時の出血は早期発見につながる重要なサインとなります。
子宮体がん
子宮体がんは、子宮内膜から発生するがんで、不正出血やおりものの異常が初期症状として現れることが特徴です。
不正出血は突然起こることが多く、排出までに時間がかかることで黒っぽい経血として見られる場合があります。
また、閉経後の女性に多く発症し、特に閉経後の出血は子宮体がんの可能性が高いため注意が必要です。
さらに、月経周期とは異なるタイミングでの出血や、量や色の変化も見逃せません。ホルモンバランスの乱れや肥満、糖尿病などがリスク要因として知られています。
早期発見で治療の成功率が大幅に向上するため、不正出血や異常を感じた場合は速やかな婦人科の受診が重要です。
子宮内膜症
子宮内膜症は本来子宮内にあるべき子宮内膜組織が、卵巣や腹膜など子宮以外の場所で増殖する疾患です。
生理痛が年々悪化し、不正出血や月経過多が見られるほか、経血が排出されるまでに時間がかかることで、黒っぽい色になる場合もあります。
また、卵巣内に古い血液が溜まり『チョコレート嚢胞』を形成することがあり、これが破裂すると激しい腹痛を伴います。
不妊症との関連も指摘されており、約半数の患者に不妊傾向が見られます。
治療には薬物療法(ホルモン療法や鎮痛剤)や手術療法(腹腔鏡手術)があり、症状やライフステージに応じて選択されます。
更年期障害
更年期は、女性の身体が閉経に向けて変化する過程であり、ホルモンバランスの乱れによって生理周期や経血量に変化が生じます。
更年期には、少量の黒っぽい出血が続くことがあり、これはエストロゲン分泌の低下によるものです。
多くの場合、心配は不要ですが、出血が長期間続いたり、不正出血が頻発する場合は注意が必要です。
感染症
膣炎や骨盤内炎症性疾患などの感染症は、黒っぽい経血を引き起こす原因となることがあります。
これらの疾患では、異臭や腹痛を伴うケースが多く、放置すると症状が悪化し、慢性的な炎症や癒着を引き起こす可能性があります。
性感染症(クラミジアや淋菌など)が原因の場合もあり、これらは女性の不妊症や子宮外妊娠につながるリスクがあるため注意が必要です。
黒い血が気になる方には月経カップの使用がおすすめ?

黒っぽい経血が気になる方には、月経カップの使用が一つの選択肢としておすすめされることがあります。
ナプキンやタンポンを使用している場合、経血が空気に触れる時間が長くなることで、酸化して色が濃くなりやすくなります。
一方、月経カップは膣内で経血を直接溜めるため、空気との接触が少なく、酸化による色の変化が起こりにくいのが特徴です。
生理用品によって経血が酸化して黒くなるのを防ぎたい方は、月経カップの使用もひとつの選択肢だといえます。
黒い血を予防するためのセルフケア

黒い経血は多くの場合、酸化や血流の滞りが原因で発生します。これを予防するためには、日常生活でのセルフケアと生活習慣の改善が重要です。
ここでは、具体的な対策をご紹介します。
身体を温めて血流を促進する
冷えは血流を滞らせる大きな原因となり、黒い経血につながることがあります。
身体を温める習慣を取り入れることで、血流を改善し、経血の排出をスムーズにできるでしょう。
シャワーだけで済ませるのではなく、38〜40℃程度のぬるめのお湯に10〜15分ほど浸かると全身の血流が促進されます。
また、生姜やシナモンを使った温かい飲み物を飲むと、内側から身体を温めることが可能です。
低用量ピル
ホルモンバランスを整え、生理周期を安定させることで、不正出血や酸化による黒っぽい経血を軽減します。
ただし、副作用や個人差もあるため、服用中に異常を感じた場合は早めに医師へ相談しましょう。
また、セルフケアと組み合わせて健康的な生活習慣を心掛けることで、より快適な生理期間を過ごせます。
イソフラボンを含む食材を意識的に摂取する
イソフラボンは、大豆製品に多く含まれる成分で、女性ホルモンのエストロゲンに似た働きをもつため、ホルモンバランスを整えるのに役立つと考えられています。
ホルモンバランスが安定すると、生理周期が規則的になり、経血の排出がスムーズになることで黒い経血の予防につながります。
具体的には、豆腐や納豆、豆乳、味噌などの食品を日常的に摂取するのがおすすめです。
特に更年期やホルモン変動が激しい時期に積極的に取り入れると、生理不順や不正出血の改善が期待できます。
まとめ
生理中の黒い経血は、酸化やホルモンバランスの乱れによる自然な現象であることが多いですが、時には婦人科系疾患のサインである可能性もあります。
不正出血や長引く経血、異臭や腹痛を伴う場合には注意が必要です。原因として子宮筋腫や子宮内膜症、感染症などが挙げられます。
セルフケアとして身体を温めたり、イソフラボンを含む食材を摂取することが効果的ですが、異常を感じた際は早めに医療機関を受診しましょう。
三軒茶屋ウィメンズクリニックでは、生理に関するお悩みや黒い経血の原因について丁寧に診察を行っています。
最新の検査機器と経験豊富な医師が、ホルモンバランスの乱れや婦人科系疾患の早期発見・治療をサポートいたしますので、不安な症状がある方はぜひお早めにご相談ください。
