不妊治療の保険適用範囲はどこまで?適用条件と適用されない検査・注意点を解説
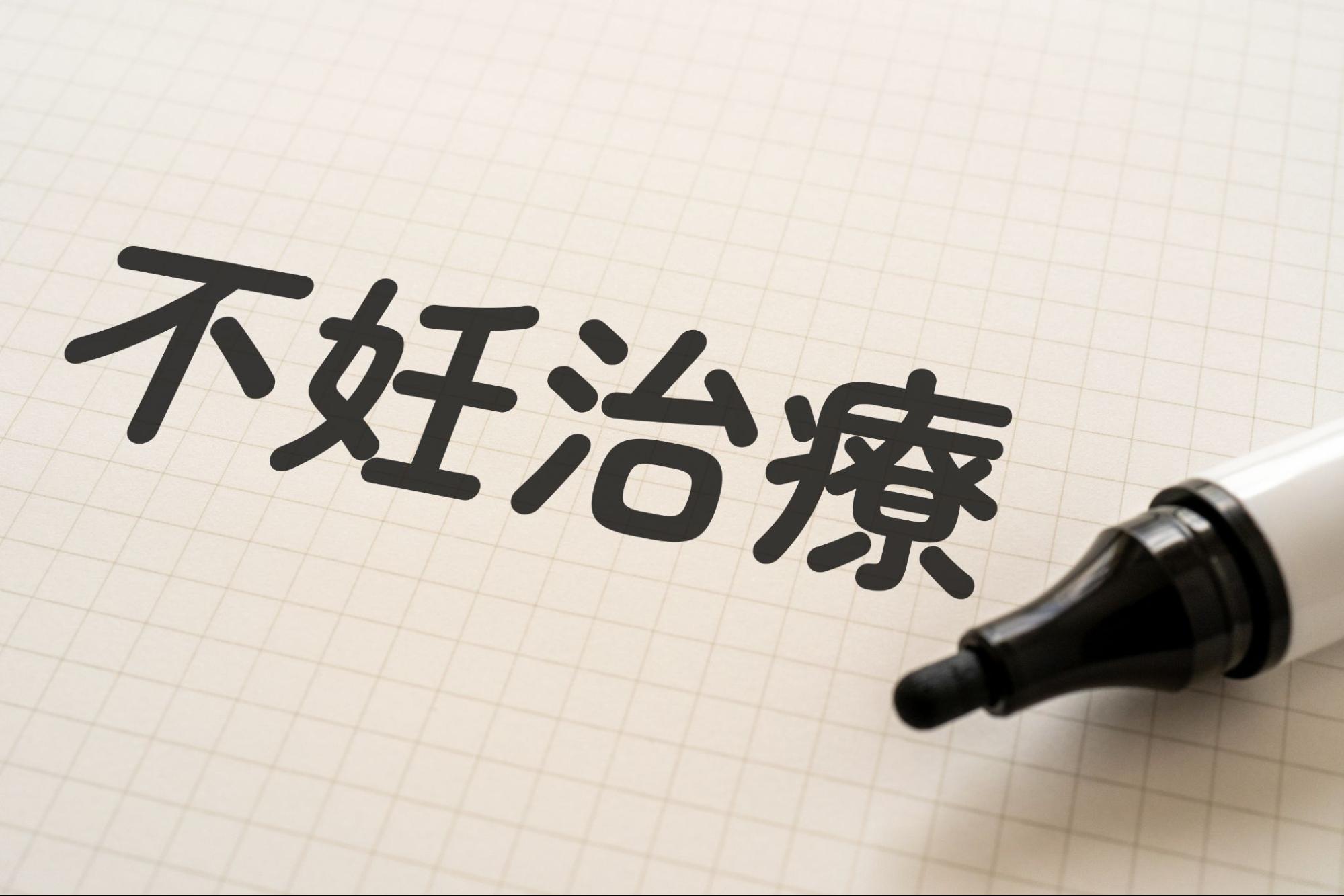
2022年4月に不妊治療の保険適用範囲が拡大したことで、不妊治療にかかる医療費が健康保険適用となり、多くの検査や治療が原則3割負担で受けられるようになりました。
2022年4月以前の不妊治療は高額の費用がかかり経済的な負担が大きかったため、不妊治療を行うハードルは高いものでしたが、保険適用により検討しやすくなったといえます。
子どもを授かりたいと願っていても経済面で不安があり不妊治療を諦めていたという方にも、朗報といえるかもしれません。
しかし、不妊治療の保険適用には、適用範囲外の治療法や保険適用される条件などがあるため、注意が必要です。
この記事では、2022年4月に拡大された不妊治療の保険適用範囲に加えて、適用条件、注意点などを解説します。
不妊治療を検討中で保険適用について知りたい方はぜひご覧ください。
2022年4月から不妊治療の保険適用範囲が拡大

2022年4月以前の不妊治療は、不妊の原因を探るための検査のみが保険適用とされ、それ以外のタイミング法や体外授精などの治療はすべて自費で支払われることになっていました。
不妊治療を行うには非常に高額な費用が必要となり、精神的な負担に加えて経済的な負担もかかっていたのです。
しかし、2022年4月に不妊治療の保険適用範囲が拡大され、タイミング法などの一般不妊治療と、体外受精などの近年で進歩した不妊治療法である生殖補助医療(ART)が保険適用範囲となりました。
ここでは、現在の不妊治療の保険適用範囲について紹介します。
どの検査や治療が保険適用になるのかわからないという方は、ぜひ参考にしてください。
不妊治療の保険適用範囲
不妊治療の保険適用範囲は、不妊の原因を探る初期検査、一般不妊治療、生殖補助医療(ART)です。
ここでは、一般的にどの治療内容が保険適用されるのかについて、治療の詳細も含めて解説します。
保険適用の範囲であっても、クリニックによって高度な医療技術や保険適用外の薬剤を使用するために自費での自由診療となる場合もあります。
診察所見
初回診察で行われる、不妊治療の原因を特定するために行う検査です。
代表的な女性側の検査は経膣超音波検査です。プローブと呼ばれる細長い器具を膣の中に入れ、子宮や卵巣の状態を観察します。
他にも、性交後の精子が膣内にたどり着いたかがわかるフーナー検査などがありますが、クリニックによってできる検査内容が異なるため、医師との相談が必要です。
精子所見
精液検査を行い、精液の量や精子濃度、運動率、精子の形態などを調べます。
精液検査により、男性側の原因のひとつである無精子症や乏精子症などの所見の有無がわかります。
画像検査
子宮の入り口からチューブを挿入し、造影剤を入れながらX線で卵管の動きを見る子宮卵管造影検査と呼ばれるものです。
精子と卵子が出会う唯一の通路である卵管に問題がないか、他の組織との癒着などがないかを調べる検査です。
血液検査
感染症の検査をするとともに、女性・男性ともにホルモンの数値を調べるための採血を行います。
女性の場合は、月経周期に応じてホルモン検査ができるかが決まるため、複数回に分けて採血を行うことがあります。
タイミング法
タイミング法とは、検査の結果、男性、女性ともに異常が認められなかった場合に、医師が排卵日を予測し、性交のタイミングを指導する方法です。
超音波検査や尿検査などにより、排卵日を特定し、自然妊娠を測るためのタイミングについて指導し、妊娠しやすさを向上させるための排卵誘発剤を使用することもあります。
ホルモン療法
ホルモン検査によって、ホルモンバランスに乱れがあった場合には、ホルモン剤を投与して月経周期を整え、自然な妊娠を促す方法(ホルモン療法)が検討されます。
漢方療法
漢方薬によっては不妊の原因を改善する効果があるため、自然妊娠を促すために漢方薬が処方されることがあります。
不妊の原因がはっきりしない場合にも効果的です。
人工授精(AIH)
人工授精とは、医師によって特定された妊娠しやすい日に、洗浄・濃縮したパートナーの精子を子宮内に注入する方法です。
数回のタイミング法ののち妊娠に至らなかった場合や、フーナーテストの結果が良くなかった場合、精液検査の結果が芳しくなかった場合に人工授精へ移行します。
採卵
採卵は、排卵の直前に膣の中に挿入したプローブによって、卵巣から卵子を体外に取り出す方法です。
採卵の前に卵巣を刺激する方法は複数あり、どの方法を採用するかは個人の状態によってさまざまです。
卵巣刺激法は以下のような種類があります。
| 完全自然周期 | 排卵誘発剤を使用しない方法 |
| クロミッド法 | 低刺激の薬剤を服用、注射を併用する方法 |
| レトロゾール法 | レトロゾールを内服し、女性ホルモンを一時的に低下させ、男性ホルモンを増加させることで卵胞発育を促す方法 |
| ロング法 | 点鼻薬と注射を使い自然排卵を抑えて複数の卵子を育てる方法 |
| ショート法 | 点鼻薬と注射を使い自然排卵を抑えて複数の卵子を育てる方法。ロング法よりも短い期間で卵巣刺激を行う |
| アンタゴニスト法 | 月経3日目から注射と内服薬の服用を行い卵子を発育させ、排卵を抑えて卵子の発育を促す方法 |
| PPOS法 | 卵巣刺激の際に黄体ホルモン剤を併用する方法 |
どの卵巣刺激法が適しているかは、ホルモンの数値や卵巣の反応によって医師が判断します。
体外受精(IVF)
体外受精は、採卵した卵子をシャーレに入れて、男性から採取した精液の中から活発な精子を選び、卵子にふりかけて受精を促す治療です。
受精卵が胚になったところで子宮に移します。
顕微授精(ICSI)
体外受精で受精できなかった場合には、顕微授精が検討されます。
顕微授精とは、顕微鏡を見ながら1個の卵子の中に1個の精子を直接注入することで受精させ、子宮に戻す方法です。
受精卵・胚培養
体外受精、顕微授精で受精が成立した受精卵を胚になるまで培養器で培養することを胚培養といいます。
胚凍結保存
胚凍結保存は、体外受精などで採取した精子や胚を液体窒素によって凍結させて保存する方法です。
胚凍結保存を行う場合には、凍結保存管理料がかかる場合があります。
胚移植
受精卵が胚になった段階でカテーテルを使用して子宮に移植する方法を胚移植といいます。
一般的に、凍結保存した胚、新鮮な胚、どちらにおいても子宮の内部の状態やホルモンの条件を整えて行うことがほとんどです。
アシステッドハッチング(孵化補助)
体外で受精された受精卵が胚になり、子宮に戻す前に、胚を保護する役目を持つ透明帯を切開することで、着床成功率を上げる方法です。
アシステッドハッチングには、機械的アシステッドハッチング、レーザーアシステッドハッチング、科学的アシステッドハッチングの3種類があります。
受精卵の状態によって、どの方法を使うか医師が判断します。
不妊治療の保険適用治療と併用できる先進医療

不妊治療には、さまざまな治療法や検査があり、その方法は日々進化を続けています。
なかでも先進医療と呼ばれる検査や治療は、国に認められた高度な医療技術であり、保険適用治療と併用することができます。
ただし、保険適用された治療と併用した場合、先進医療分の医療費は自費となり、3割負担にプラスして自費で医療費を支払う必要があります。
不妊治療の先進医療は以下のようなものがあります。
| タイムラプス法 | 培養器に入れたまま胚の観察・培養ができる技術 |
| SEET法 | 受精卵と培養液を凍結保存し、融解したものを子宮に注入する方法 |
| ERAテスト | 子宮内膜が受精卵を受け入れられる状態かを調べる検査 |
| EMMAテスト | 子宮内に存在する細菌の集合体(フローラ)が妊娠に適しているか調べる検査 |
| ALICEテスト | 慢性子宮内膜炎の原因になる細菌を調べる検査 |
これらの先進医療を取り入れるかどうかは、医師と相談のうえ決定するものです。
クリニックによっても取り扱っている先進医療には幅があるため、クリニック選びの際には注意深く調べることが大切です。
不妊治療の保険適用になる条件

不妊治療の保険適用は、すべての人が対象になるわけではありません。
保険適用に際しては、年齢などの条件があり、治療内容によっても適用できる回数が異なります。
条件は一般不妊治療と生殖補助医療で分けられており、下記で詳しく説明します。
一般不妊治療
タイミング法や人工授精の一般不妊治療は、保険適用における年齢制限や回数制限はありません。
生殖補助医療(ART)
体外受精・顕微授精といった生殖補助医療が保険適用になる条件には、年齢制限と回数制限があります。
年齢制限については、治療開始時点の女性の年齢が43歳未満であることが条件です。
例えば、不妊治療を42歳で開始し、治療期間中に43歳になった方の場合、その周期の胚移植までが保険適用となり、次周期からは自費となります。
回数制限に関しては、下記の表をご覧ください。
| 初めて治療を開始した年齢(女性) | 保険適用回数の上限 |
| 40歳未満 | 1子ごと通算6回まで |
| 40歳以上43歳未満 | 1子ごと通算3回まで |
回数は、胚移植の実施回数で数えます。採卵の回数ではないことに注意しましょう。
回数制限は、出産した場合にリセットされ、次の子を希望する際には再度回数が適用されます。
生殖補助医療の場合、保険適用には年齢制限や回数制限の条件があるため、不妊治療を検討する方はできるだけ早く治療を始めたほうがメリットがあるといえるでしょう。
不妊治療の保険適用の注意点
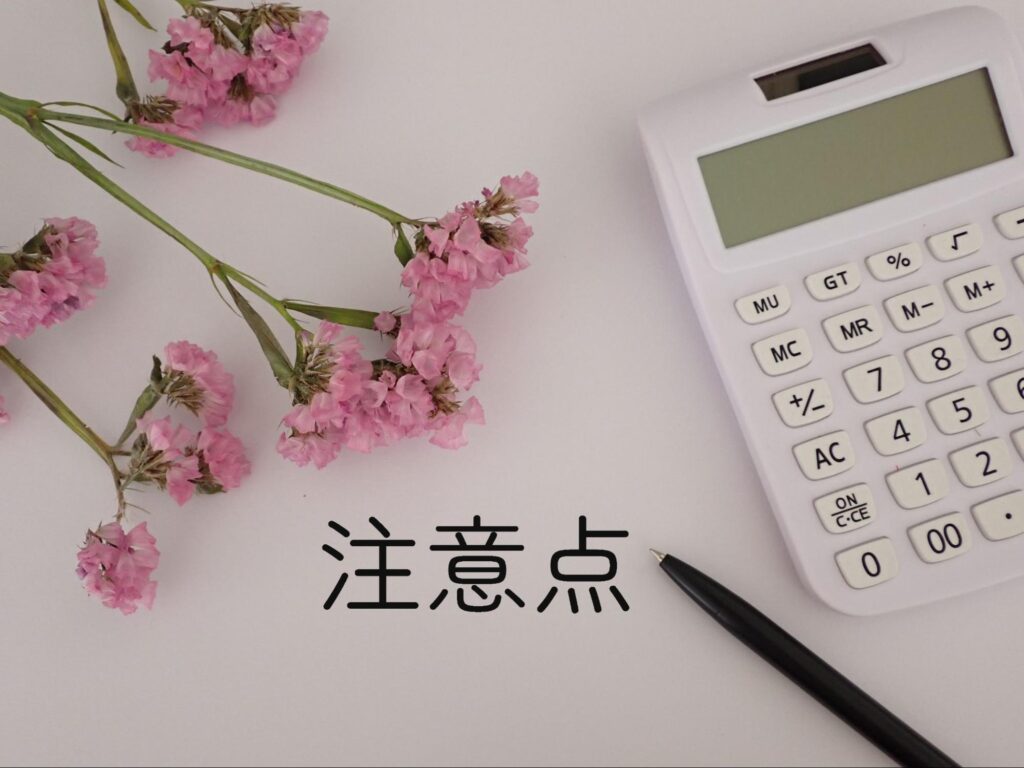
不妊治療の保険適用には、注意点がいくつかあります。
どのような点に注意が必要なのか、詳しく見ていきましょう。
保険診療と自由診療の併用は原則禁止
不妊治療における先進医療と保険診療の併用は認められています。
しかし、保険診療とも先進医療とも認められていない、その他の医療技術や精密機器などを使用する治療法は自由診療となり、治療費は全額自己負担となります。
保険診療で治療の効果が出なかった方や効果をより高めたい方のために自由診療という選択肢はありますが、保険診療と自由診療の併用は原則禁止です。自由診療を併用した場合には、保険適用分の治療も自由診療扱いとなり、全額自己負担となります。
地方自治体で助成金がある場合も
先進医療と保険診療を併用する場合、在住している地方自治体によっては助成金が出る場合もあります。
先進医療だけでなく、国が定めた保険適用の回数に加えてさらに1回分の助成金が出たり、一般不妊治療へのさらなる助成金が出たりする場合もあります。
不妊治療を検討する際には、保険適用だけでなく地方自治体の助成金も調べてみましょう。
保険適用の回数を超えた場合は自費に
不妊治療の保険適用は年齢、胚移植の回数で制限があります。
不妊治療中に43歳になった場合、その周期の胚移植までが保険適用され、次の周期は自由診療です。
また、年齢によって定められた回数を超えた場合も、次の周期からは自費での胚移植となります。
まとめ
不妊治療で保険適用になる範囲が拡大され、タイミング法や人工授精などの一般不妊治療と生殖補助医療の治療費が3割負担の保険適用となりました。
しかし、生殖補助医療に関しては、年齢制限や回数制限などの条件があるため、不妊治療を検討している方は、できるだけ早く治療を行うことが推奨されます。
『三軒茶屋ウィメンズクリニック』では、保険適用内の治療に加え先進医療の治療方法も取り扱っています。
患者さん一人ひとりの状態に合わせたオーダーメイドの不妊治療を行い、誠実な医療を心がけています。不妊治療を検討したいけれど保険適用の範囲でできるのかという不安がある方は『三軒茶屋ウィメンズクリニック』にぜひご相談ください。
