月経周期とは?数え方やずらしたい時の方法を解説

旅行などの予定があるから月経周期をずらしたい、いつ月経が来るのか知りたいというお悩みを持つ方もいるかもしれません。
月経周期は人によって異なり、他にもさまざまな要因で月によって変化することもあります。
自分の月経周期を知っておけば、スケジュールを立てやすくなる、排卵の時期を知ることができる、病気を早めに発見することができるなどのメリットが多くあります。
この記事では、月経周期の概要や計算方法、周期のフェーズごとの心や身体の変化、月経をずらす場合の方法などについて紹介します。
月経周期とは

月経周期とは、生理の開始日から次の生理が始まる前日までの日数を指します。
生理は、妊娠のために成熟した子宮内膜が剥がれ落ちることで起こります。
女性ホルモンの働きによって一定のサイクルで排卵が起こると、子宮内膜は受精卵を受け止める準備のために厚さを増します。
しかし、妊娠がその周期中に起こらなければ、また新しい子宮内膜をつくるために古い内膜は剥がれ落ちて血液と一緒に体外に排出され、その現象が生理と呼ばれます。
生理の開始日から次の生理までは、身体の中で上記のような現象が起きています。
平均的な月経周期
平均的な月経周期は25~38日で、生理が続く期間は3~7日です。
生理周期が24日以下のものを「頻発月経」、39日以上のものを「稀発月経」と呼びます。
多くはホルモンバランスの乱れが原因ですが、病気が隠れている可能性もあるため、気になる症状がある場合は早めに婦人科を受診しましょう。
月経周期の4つのフェーズと心や身体の変化

生理開始日が近くなると毎回イライラする、眠い、身体がだるい、などの症状に悩まされる方もいるのではないでしょうか。
このような女性特有の症状は、女性ホルモンの分泌状態によって分けられる月経周期の4つのフェーズに関係しています。
月経周期は卵胞期(増殖期)、排卵期、黄体期(分泌期)、月経期の4つの期間に分けられており、期間ごとに心と身体に変化をもたらすことが多いです。
ここでは、4つの期間の体内で何が起こり、心と身体にどのような変化があるのかについて詳しく解説します。
月経期
月経期は出血が始まってから終わるまでの期間を指します。
着床しなかった時は、子宮内膜が剥がれ落ちて血液と一緒に体外へと排出されます。これが生理(月経)です。
女性ホルモンの分泌が最も少ない時期で、下腹部痛、腰痛、吐き気、下痢、イライラ、頭痛、貧血、だるさ、むくみ、肌あれなど不快な症状が起こりやすい時期でもあります。
憂鬱な気分になりやすい時期ですが、生理が終わりに近づくにつれて、卵胞ホルモンの分泌が始まり、落ち込んだ気分から抜け出せます。
思春期や更年期はホルモンバランスが安定しないため、月経期間も経血量もばらつきが出ることがあります。
月経中に気になる症状があれば早めに婦人科を受診しましょう。
卵胞期(増殖期)
卵胞期(増殖期)には、脳下垂体から分泌される卵胞刺激ホルモンの働きにより、卵巣にある原始卵胞のひとつが発育しはじめます。
卵胞が発育するにつれ卵胞ホルモンが分泌され、子宮内膜が少しずつ厚くなっていきます。
卵胞期(増殖期)は、心身ともに最も安定している時期です。
肌や髪の状態もよくなり、気持ちも落ち着いてポジティブに過ごすことができ、ダイエットの効果も出やすいなど、何かを始めるには最も適した時期です。
排卵するまでの間、基礎体温が低温を示すのも特徴です。
排卵期
卵胞ホルモンの分泌がピークに達すると、黄体化ホルモンが分泌され、卵胞から卵子が飛び出します。これが排卵です。
排卵には急激なホルモンの変化がともなうため、感情の起伏が激しくなり、冷え、むくみ、腹痛、身体のだるさなどの体調不良が起こることもあります。
また、排卵の前後に痛みを感じることがあるという方もいます。下腹部の左右どちらかで鈍い痛みが数分から数時間続くのが特徴ですが、詳しい原因はわかっていません。
排卵日前後は睡眠をしっかりとる、生活リズムを整える、身体を冷やさないようにする、ストレスを発散するなどに注意して、体調不良の改善に努めましょう。
ただし、日常生活に支障が出るレベルの不調が出た場合は、早急に婦人科で診察を受けることが大切です。
黄体期(分泌期)
排卵後、卵胞は黄体という組織に変化して黄体ホルモンの分泌を始めます。
妊娠に適した環境にするため、黄体ホルモンと卵胞ホルモンの作用で子宮内膜は厚く柔らかくなります。
子宮内膜には、着床に備えて受精卵のための水分や栄養素がためこまれるようになり、これが月経前にむくみやすく、太りやすいことの原因です。
妊娠が成立した場合、黄体はそのまま維持されますが、成立しなかった場合には黄体ホルモンと卵胞ホルモンの分泌は低下し、子宮内膜が剥がれる月経が始まります。
黄体期(分泌期)は、女性ホルモンの影響で心も身体も不安定になる時期です。
生理前症候群(PMS)により、乳房が張る、痛む、乳首が敏感になる、頭痛、肩こり、腰痛、下痢、ニキビ、肌あれなどの不快な症状が起こる人もいるかもしれません。
そのほかにも、イライラ、憂うつ感、不眠、眠気、過食などの症状がおこりやすくなります。
生理前と呼ばれるこの時期は、無理をせずリラックスできる環境でゆったりと過ごすことを心がけましょう
月経周期の計算方法
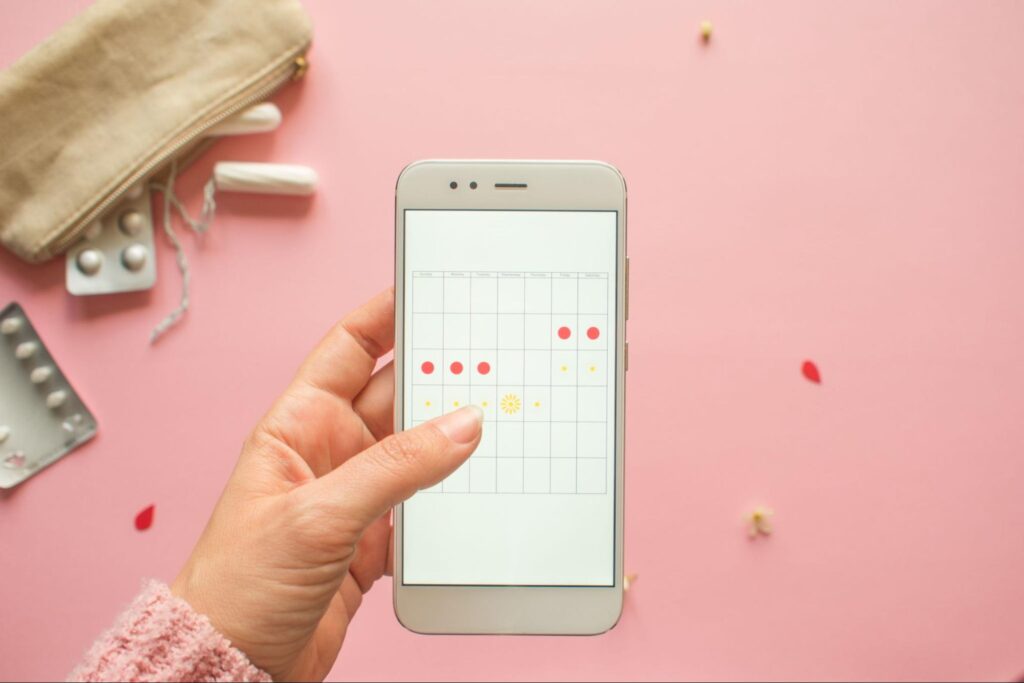
月経周期は人によってばらつきがあります。
自分の月経周期を知っておくと、スケジュールの把握がしやすくなったり、生理前による体調不良の予測や生理不順かどうかを見極めることもできます。
月経周期は以下の方法で比較的簡単に計算できます。注意点として、出血が始まる生理の開始日を起点として、毎回きちんと記録をつけましょう。
- カレンダーなど日付がわかるものを準備する
- 生理が始まった日に『1』と記入する
- 次の日は『2』、以降も1日経過するごとに『3、4、5……』と記入していく
- 次の生理が始まった日を『1』と記入する
- その後の手順を繰り返す
例えば、1月1日に生理が始まり、1月31日に次の生理が来た場合の月経周期は30日となります。
生理周期は、ホルモンバランスや体調などによって大きく変化し、月によって周期も大きく変わることがあるため、1回分のデータでは判断しないようにしましょう。
より正確な周期を知るために、3回以上のデータを取り、平均値から自分の月経周期を割り出すことをおすすめします。
ただし、生理周期がバラバラな場合には、平均ではなく、それぞれの周期の日数が重要です。
生理周期が12日になったり40日になったりとばらつきが続く場合には、婦人科を受診しましょう。
毎月、生理が来た日を入力すれば自動で生理周期を計算してくれるアプリを活用するのもおすすめです。
月経をずらす方法は?

大切なイベントが生理と被りそうなときなどに、月経を移動させたいと思う方も少なくありません。
生理日は、ホルモン剤(低用量ピル、中用量ピル)によってコントロールできます。
ここでは、月経を遅らせる方法、月経を早める方法、副作用について解説します。
月経を遅らせたい場合
生理を遅らせるためには中用量ピルを使うことが多いです。
ずらしたい生理開始予定日の5日前位から中用量ピルを飲み始めます。
ピルを飲んでいる間は生理が止まり、服用を止めると、2〜3日で消退出血(軽い生理のような出血。平均5日程度で治まる)が起こります。
中用量ピルは最長で7日程度生理を遅らせることが可能といわれていますが、個人差があるため、中用量ピルを飲んでいる途中で生理が来たらすぐに飲むのをやめましょう。
生理を遅らせる場合、本来生理が来ているはずの期間はピルを内服し続ける必要があるため、遅くとも生理予定日の1週間前には受診するようにしましょう。
また、生理を遅らせる方法の場合、排卵日以降にピルの内服を始めることになるので、妊娠の可能性がある場合には内服できないことに注意が必要です。
月経を早めたい場合
生理を早めたい場合には、早めたい生理の一つ前の生理が始まった時点から低用量ピルを飲み始めます。
本来の生理予定日の10日前くらいまで飲み続け、ピルの内服を中止すると、2~3日後に消退出血が起こります。
消退出血の次の生理は、28日周期の方であれば28日後にきます。
月経をずらすことの副作用
月経をずらすこと自体には大きな問題はなく、排卵がきちんとあればピルの内服を止めると数日で消退出血が起こります。
その後の生理ももとの生理周期と同じ間隔で起こります。
月経をずらす際に使われるピルには、吐き気や頭痛などの副作用が起こる可能性があります。
また、非常にまれですが、血栓症を引き起こす可能性もあります。
ピルを飲んでいて気になる症状がある場合には、早めに婦人科を受診しましょう。
月経周期に関する気になる疑問
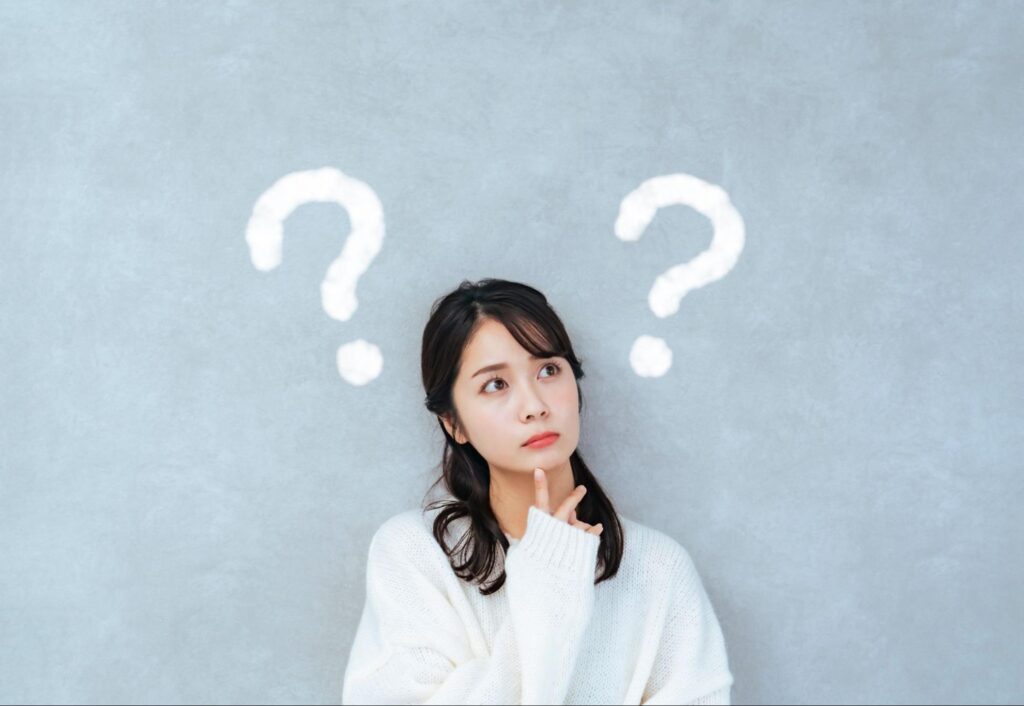
ここでは、月経周期に関する気になる疑問をまとめました。
排卵のタイミングはいつ?
妊娠を考えている方にとって知りたい排卵のタイミングは、オギノ式と呼ばれる計算方法と基礎体温の計測の二つの計測方法があります。
オギノ式では「生理周期 – 14日 = 生理が始まってから排卵が始まるまでの日数」としており、例えば28日周期の人は「28−14=14」なので、生理が開始してから14日後が排卵日となります。
しかし、ホルモンバランスが乱れ月経周期に乱れがある場合は、この計算方法で排卵日を計測するのが難しくなるため、基礎体温を毎日つける方法もおすすめです。
基礎体温は婦人体温計を用いて、朝目が覚めたら起き上がる前にすぐ口内で検温しましょう。
排卵は、基礎体温の低温相から高温相に変わるタイミングで起こります。
基礎体温が上昇する3日間に排卵が起こることが多いといわれています。
月経周期が乱れるのは病気?
正常な月経周期は25~38日ですが、月経周期が短かったり長かったりすることを生理不順といいます。
生理不順の多くは、ホルモンバランスの乱れで起こりますが、中には子宮がん、子宮筋腫などの病気が隠れている可能性があります。
初潮から数年は8割の方が生理不順で、20代前半になると周期が安定してきます。
以下の表は年代別の受診の目安です。
| 20歳以下の場合 | 3か月生理が来なければ受診 |
| 20~45歳の場合 | 毎回生理不順気味なら、ホルモン値などを調べるため受診 |
| 45歳以上の場合 | 生理が不規則になったら、更年期障害や婦人科疾患の可能性があるため早めに受診 |
月経周期が乱れた際は、自己判断をせずに早めに婦人科を受診することが大切です。
月経はいつからいつまで続きますか?
初潮の平均年齢は12.3才、閉経の平均年齢は50.5才といわれています。
初潮と閉経には女性ホルモンがかかわっています。
初潮から20歳くらいまで女性ホルモンの量は増加し、妊娠に適したピークを20歳代で迎えます。
その後、30代後半から少しずつ女性ホルモンの分泌は減少をはじめ、更年期の始まりから10年くらいかけて女性ホルモンがなくなっていきます。
まとめ
月経周期は、人によって異なりますが、正常な月経周期は25~38日です。
月経周期には女性ホルモンの分泌による4つのフェーズがあり、その時期によって心と身体に変化が起こります。
なかでも月経が始まる前の黄体期は非常に不安定になりやすく、不調が起こることも少なくありません。
日常生活に支障が出るほどの痛みや辛さの場合には我慢せずに早めに婦人科を受診しましょう。
『三軒茶屋ウィメンズクリニック』は、不妊治療はもとより、婦人科治療においても、患者さんの心に寄り添い信頼される治療を目指しています。
駅から徒歩3分とアクセスも良く、土曜日や夜間も診察を行っています。
月経周期について気になることがある方は、『三軒茶屋ウィメンズクリニック』にお気軽にご相談ください。
