生理前に眠くなるのはなぜ?眠気の原因と今日から出来る対策を解説

「生理前になると、どうしてこんなに眠いの?」そう思ったことはありませんか?
毎月のように襲ってくる、強い眠気やだるさによって、仕事や家事に集中できなかったり、朝起きるのがつらかったりする方はすくなくありません。
「怠けているわけじゃないのに、なんだか自分を責めてしまう……」そんな風に感じている方もいるのではないでしょうか?
実は、この生理前の強い眠気には、女性ホルモンの変化をはじめとした、いくつかのはっきりとした原因が存在しています。
この記事では「生理前に眠くなる理由」から、「今日からできるセルフケアの方法」、さらには「医療機関の力を借りるタイミング」まで、丁寧に解説していきます。
読むことで、あなた自身の体と心をもっと大切にできるようになりますように。
生理前に眠くなる原因
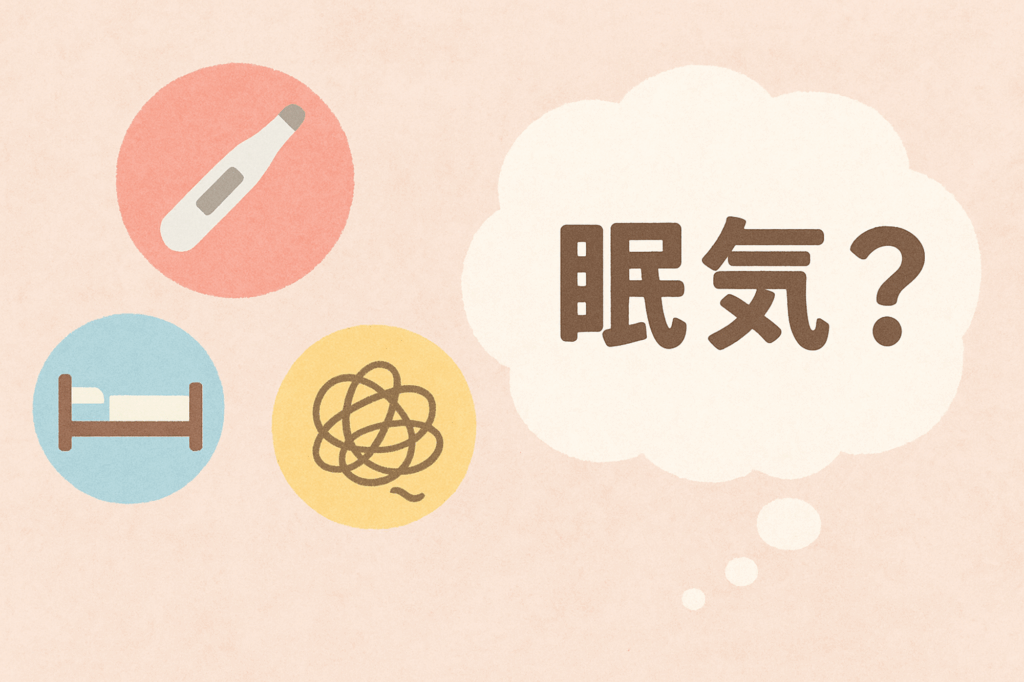
生理とともにやってくる眠気。その眠気は、いくつかの原因が重なって起きている事がほとんどです。原因について項目ごとにお伝えします。
ホルモンバランスの変化による眠気
生理前の眠気の大きな原因は、プロゲステロン(黄体ホルモン)の影響です。
生理周期は約25~38日あり、その間に女性ホルモンは大きく変動しています。
特に排卵後から生理が始まる直前までは「黄体期」と呼ばれ、妊娠に備えてプロゲステロンの分泌が盛んになります。
このプロゲステロンは、体温を上げたり、水分を溜め込んだりする働きのほかに、「眠気を促す」作用もあると言われています。
妊娠初期に眠くなるのと同様に、プロゲステロンは心と身体を休ませようとする方向に働くのです。
また、プロゲステロンが増えることで、脳内の覚醒を維持する神経伝達物質である「セロトニン」や「ドーパミン」の分泌バランスが乱れやすくなります。
その結果、普段よりも気分が沈んだり、やる気が出なかったり、ぼんやりとした状態になりやすいのも、眠気を感じる原因です。
自律神経の乱れと体温上昇
生理前は自律神経のバランスが乱れやすく、それにより睡眠の質が低下し、眠気につながります。
自律神経は、体温調整・血流・睡眠リズム・消化などを司る重要な役割を担っています。
これが乱れると、日中に眠気を感じたり、だるさや頭痛、集中力の低下といった不調があらわれやすくなります。
黄体期に入ると、プロゲステロンの影響で体温が約0.3〜0.5℃ほど上昇します。
人は通常、深部体温(内臓の温度)が下がると眠りに入りやすくなるのですが、生理前は体温が高いままで推移するため、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。
さらに、生理前にエストロゲンの分泌量が減少すると、自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスが乱れやすくなります。
睡眠の質が低下している
「ちゃんと寝ているのに眠い……」そんなときは、睡眠の“質”に問題があるかもしれません。
生理前は、腹部の張り、胸の痛み、気分の落ち込み、イライラなど、精神的にも身体的にも不調が出やすい時期です。
これらの症状によって、夜中に何度も目が覚めたり、寝つくまでに時間がかかったりして、深い眠り(ノンレム睡眠)を十分にとることができないケースもあります。
また、PMS(月経前症候群)の症状のひとつとして、「睡眠障害」が現れる人もいます。
眠りが浅くなることで、脳や身体が十分に回復できないことも日中に強い眠気を感じる原因です。
生理前のどの時期に眠気が強くなるのか

特に眠気が強く出るのは、排卵後から生理が始まる直前までの「黄体期(こうたいき)」です。
生理周期は一般的に25~38日程度で、大きく「卵胞期」「排卵期」「黄体期」「月経期」の4つに分けられます。
この中で、眠気の症状が出やすいのが「黄体期」です。
黄体期は、排卵が終わった直後から始まり、生理が始まるまでの約2週間に相当します。
この時期、体は妊娠に備えるためにプロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌が増加し、以下のような影響が現れます。
| 要因 | 概要 | 主な影響・症状 |
|---|---|---|
| 体温上昇 | プロゲステロンの作用で基礎体温が0.3〜0.5℃上昇 | ・眠気の増加・ 睡眠の質が低下しやすい(体温が高いため寝つきが悪くなる) |
| ホルモンバランスの乱れ | セロトニンやメラトニンの分泌が不安定に | ・気分の浮き沈み・不眠または日中の強い眠気 |
| PMSによる眠気 | 月経前症候群の一部として眠気が出現 | ・疲れやすい、朝起きられない・1日中ぼんやりする感覚 |
| PMDD(重度のPMS) | 月経前不快気分障害としての症状 | – 精神的な不安、怒り、抑うつ – 強い眠気やだるさで日常生活に支障 |
生理前の眠気は一時的なものとはいえ、ホルモンの自然な変化によって起こる、身体からの「ちゃんと休んで」というサインでもあります。
自分の身体のリズムを把握して、「今は黄体期だから仕方ない」と受け入れることで、気持ちも少し楽になるかもしれません。
毎月の生理周期を記録しておくと、眠気が強くなる時期を予測しやすくなり、スケジュール調整やセルフケアにも役立ちます。
日常でできる5つのセルフケア対策

生理前の眠気を和らげるためには、毎日のちょっとした工夫がとても大切です。
以下の5つのセルフケアは、どれも今日から取り入れられる方法ばかりです。無理せず、自分にできることから試してみましょう。
質の高い睡眠環境を整える
生理前の眠気は、夜間の睡眠の質が落ちていることが原因の一つです。寝室の環境を見直すことで、ぐっすり眠れる夜をサポートできます。
部屋は静かで暗い空間に整えましょう。光や音が気になる人は、遮光カーテンや耳栓の使用がおすすめです。
また室温も快適さに影響してきます。夏は26℃前後、冬は22℃前後が理想とされます。
睡眠環境を整えるには寝具も大切です。枕やマットレスが合わないと、肩こりや腰痛を引き起こすこともあるため、見直してみましょう。
就寝1時間前からはスマホやテレビなどの使用を控え、ブルーライトの影響を避けましょう。読書やリラックス音楽などがおすすめです。
朝の光を浴びて体内時計をリセット
人間の体内時計は、朝の光によってリセットされ、1日のリズムが整います。
これは睡眠と覚醒のバランスを調整するうえで非常に重要です。起床後はすぐにカーテンを開けて、自然光を浴びる習慣をつけましょう。
5〜10分でもベランダに出て外気に触れるだけで、体が目覚めやすくなります。
日光を浴びることでセロトニンという「幸せホルモン」も光の刺激で活性化され、心の安定にもつながります。
眠くなったら短時間の仮眠を
日中にどうしても眠くなってしまうときは、無理に我慢せず、短時間の仮眠をとりましょう。
10〜20分の仮眠は、脳をリフレッシュさせ、午後の集中力や気分を改善する効果があります。
ただし、30分以上の仮眠はかえって深い眠りに入りやすく、起床後に頭がぼーっとしてしまう「睡眠慣性」が起こるため注意が必要です。
静かな場所で横になれなくても、デスクに伏せるような姿勢でも問題ありません。アイマスクやタイマーがあると便利です。
リラックス習慣を取り入れる
心と体の緊張をほどき、ストレスを和らげることで睡眠の質も高まりやすくなります。
寝る前の軽いストレッチや深呼吸がおすすめです。副交感神経が優位になり、自然と眠気が訪れます。
アロマを活用するのもおすすめです。ラベンダー、ベルガモット、オレンジスイートなどはリラックス効果が高く、眠気を促します。
また、就寝1〜2時間前にぬるめ(38〜40℃)のお風呂にゆっくり入ると、深部体温が一時的に上がったあと、自然に下がって入眠しやすくなります。
食事と栄養にも意識を向ける
生理前はホルモンの影響で食欲が乱れたり、甘いものが欲しくなったりしやすい時期です。
栄養バランスに気を配ることで、眠気対策にもつながります。
ビタミンB6やマグネシウムはホルモンバランスを整え、PMS症状の軽減にも役立つとされています。バナナ、サバ、ナッツ類、玄米などが豊富です。
そして鉄分も重要です。鉄不足は貧血を引き起こし、日中の強い眠気やだるさの原因になります。レバー、ひじき、ほうれん草、大豆製品などを意識的に取り入れましょう。
カフェインや糖質の摂りすぎは、血糖値の乱高下や自律神経の乱れを招く可能性があるため、過剰摂取に注意が必要です。
毎日の生活に少し意識を向けることで、生理前の不調をやわらげることは十分に可能です。
自分をいたわる時間を大切にしましょう。
つらい場合は医療機関の受診も検討を

セルフケアを試しても症状が改善しない場合や、生活に支障をきたすほどの眠気・気分の落ち込みがある場合は、医療機関への相談をおすすめします。
たとえば、以下のような状態が見られる場合には、早めの受診が安心です。
・毎月決まった時期に強い眠気や倦怠感が現れる
・日常生活や仕事に支障をきたしている
・感情のコントロールが難しく、人間関係にも影響が出ている
・食欲不振、過食、不眠または過眠なども同時に見られる
これらの症状が続くと「PMDD(月経前不快気分障害)」や「うつ病」などの診断がつくこともあり、放置せずに対応することが大切です。
婦人科では、低用量ピルや漢方(加味逍遙散など)を用いた治療、また心療内科では心理カウンセリングや必要に応じた薬物療法などが受けられます。
「つらいのは私のせいじゃない」と自分に優しく声をかけ、信頼できる医師のサポートを得ながら、無理せず整えていきましょう。
まとめ
生理前の強い眠気は、多くの女性が経験するごく自然な身体の反応です。 ホルモンバランスの変化や自律神経の乱れ、睡眠の質の低下などが関係しており、自分の体をいたわるきっかけにもなります。
無理をせず、自分に合ったセルフケアを少しずつ取り入れることが、心と体を守る第一歩となります。 それでもつらい症状が続く場合には、医療機関への相談をためらわず、専門家の力を借りることも大切です。
三軒茶屋ウィメンズクリニックは、婦人科疾患や生理に関する悩みに丁寧に寄り添うクリニックです。
PMSやPMDDといった症状についても、専門の医師が一人ひとりの体調やライフスタイルに合わせてアドバイス・治療を行っています。
「これって普通のことなのかな?」「誰かに相談したいけど不安」と感じたら、お気軽に三軒茶屋ウィメンズクリニックにご相談ください。
あなたの毎日が少しでも軽やかになるよう、医療の立場からしっかりとサポートいたします。眠気に悩まされる毎日が少しでも軽くなり、笑顔で過ごせる日が増えることを願っています。
