不妊治療って何をするの?不妊治療の流れと検査内容、初診前に知っておきたい疑問を解説

不妊治療をしてみたいけれど「どのタイミングで行けばいいの?」「具体的には何をするの?」と不安に思う方もいるかもしれません。
不妊治療は、妊娠を希望しているけれどなかなか授からない場合に、その原因を探し、妊娠に繋げるための治療です。
人に言いづらい悩みでもあるため、相談することが難しいという方もいるのではないでしょうか。
ここでは、不妊治療の流れや検査内容、初診のタイミングや持ち物やよくある疑問を詳しく解説します。
安心して不妊治療を行うための参考にしてください。
不妊治療の初診の流れ

不妊治療を初めて行う方の中には、初診時の治療の流れがわからず不安を抱える方もいるかもしれません。
不妊治療の初診では、問診や不妊の原因を特定するための基本的な検査を行います。
基本検査の結果に応じて、原因疾患の治療、タイミング法や人工授精などの一般不妊治療を行い、一般不妊治療でも自然妊娠に至らなかった場合には、体外受精や顕微授精などの生殖補助医療にステップアップするのが一般的です。
まずは、初診時の流れを知っておくことがクリニックの扉を叩く勇気や安心に繋がります。
ここでは、一般的な不妊治療の初診の流れと内容について詳しく解説します。
不妊治療の初診ですること
不妊治療の初診では、医師による問診や不妊の原因を特定するための検査を行うことが一般的です。
問診でどんなことを聞かれるのか、検査はどんなことをするのかを知っておくと、クリニックでも安心して対応ができます。
以下に問診と検査の詳しい内容を解説しますので、参考にしてください。
問診
医師との問診では、以下のような質問が書かれた問診票をもとに行われます。
- 生理周期や月経日数、最終月経月
- 初潮年齢
- 結婚年齢
- 避妊期間の有無
- 過去の妊娠・出産・流産・中絶歴
- 過去の治療歴や持病
- アレルギーの有無・服用している薬の種類
- どんな治療を希望するか
基礎体温をつけている人は、基礎体温表を持参することで、問診がスムーズに進みます。
質問の中でも特に考えておきたいのは、希望する治療についてです。
それぞれの負担を考えながら、夫婦で話し合って方針を決めていきましょう。
不妊治療中は精神的な負担が大きくなりがちで、医師とのコミュニケーションを通して信頼関係を築けることで、精神的な安定や不妊治療のモチベーションにも繋がります。
医師の話をじっくりと聞き、疑問があればすぐに質問をするなど、不安なことがあれば解消していきましょう。
基本検査
不妊治療の初診では、基本的な不妊検査を行うのが一般的です。
受診するタイミングによって当日に行う検査内容が異なる場合もあります。
ここでは、不妊の原因を特定するための検査の詳細を紹介します。
基礎体温の測定
基礎体温を測定しておくと、女性ホルモンが正常に働いているかがわかりやすくなります。
月経周期の乱れを発見したり排卵日を特定したりできるため、日頃から基礎体温をつけておくことをおすすめします。
不妊治療で婦人科を受診する場合には、基礎体温表を持参することで、検査や治療の参考になります。
採血・ホルモン検査
女性の身体はホルモンの影響を受けやすく、自然に妊娠をするためにも女性ホルモンの働きが正常でないと難しい場合があります。
不妊治療の初診では、採血によるホルモン検査を行い、異常がないかを確かめます。
どの種類のホルモンについて検査するかは、以下の表をご覧ください。
| AMH(抗ミュラー管ホルモン) | 卵巣内にどれくらい卵子のもとが残っているかを示すホルモン |
| FSH(卵胞刺激ホルモン) | 卵胞の発育を促進させるホルモン |
| LH(黄体化ホルモン) | 排卵を促すホルモン |
| エストロゲン(卵胞ホルモン) | 卵巣から分泌され、排卵の準備を整える、子宮内膜を厚くする働きのあるホルモン |
| プロゲステロン(黄体ホルモン) | 子宮内膜を着床に適した状態に維持するホルモン |
これらのホルモンの数値が妊娠に適していない場合、ホルモン治療を行う場合があります。
また、血液検査ではホルモン検査の他に夫婦ともにB型肝炎、C型肝炎、クラミジア、梅毒、HIVなどの感染症の検査も行います。
感染症検査は、赤ちゃんへの感染症を防ぐためだけでなく、感染症により不妊の原因となっている可能性を見極める、不妊治療中の夫婦間での感染を防ぐ、精子を扱う場合のリスク回避が目的です。
経腟超音波検査
女性の膣内にプローブと呼ばれる器具を挿入し、子宮の形、子宮内膜の厚さ、卵胞の発育具合、排卵の有無などを観察します。
経腟超音波検査によって、子宮筋腫、子宮腺筋症、多嚢胞性卵巣症候群などの不妊の原因となる疾患があれば、確認することができるのです。
子宮卵管造影法
子宮卵管造影法は、精子と卵子が出会うための卵管という通路の流れが滞っていないかをX線で確認する方法です。
子宮の入り口から細いチューブを挿入し、造影剤を注入しながらX線で造影剤が子宮から卵管を通りおなかのなかに広がっていく様子を観察します。
通過障害があると、精子が卵子までたどり着くことができないため、自然妊娠や人工授精が難しくなります。
精液検査
男性側の原因があるかどうかを調べるために精液検査を行います。
数日間の禁欲後に精液を採取し、精液の濃度、精子の運動率、正常な形態をしているかを確認します。
不妊治療の基本検査後に進むステップと流れ
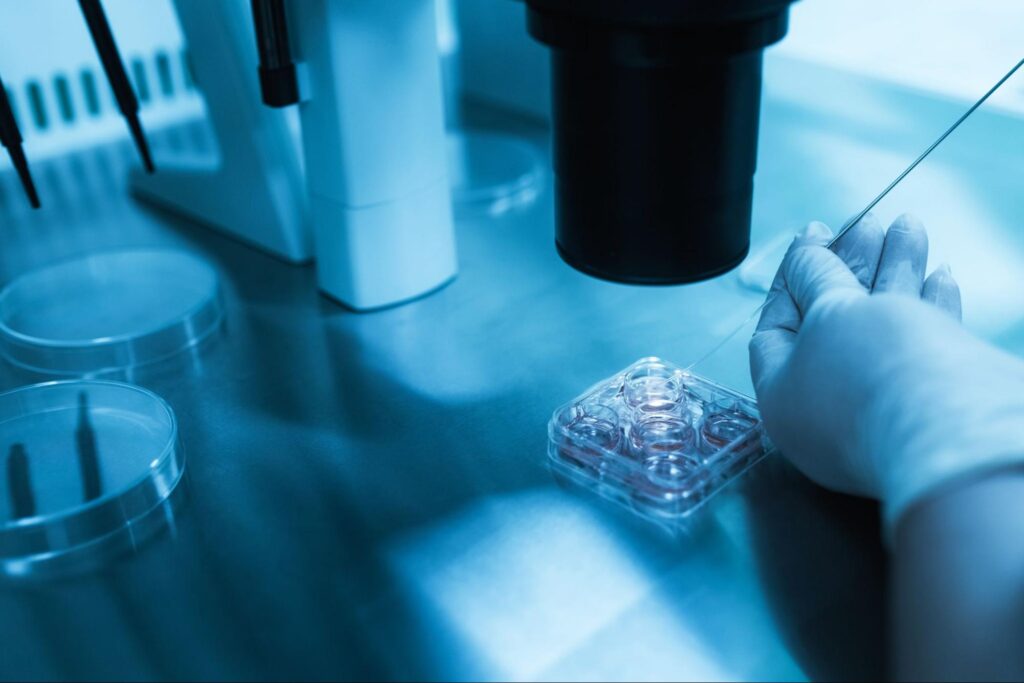
不妊治療は、基本検査が終わった後に一般不妊治療から生殖補助医療と段階的に進むのが一般的ですが、治療方針は個人差があり、誰もが同じように進むわけではありません。
例えば、検査の結果でタイミング指導での妊娠が難しいと判断された場合には、タイミング指導を行わずに人工授精から始めるケースもあります。
不妊治療はそれぞれの夫婦に合った治療を行うもののため、医師の方針に従いつつ、疑問に思ったことをきちんと聞くことが重要です。
ここでは、自然妊娠のための一般不妊治療と、その後にステップアップした際に行われる生殖補助医療の内容について紹介します。
不妊治療がどんなことをするのかわからず不安になっている方は、内容を知っておくことで安心できるかもしれません。
一般不妊治療
基本検査の後、不妊に繋がる異常が見つからなかった場合に一般的に行われることが多い治療が、身体の負担が少ないタイミング法です。
タイミング法だけでは妊娠に至らなかった場合には、人工授精へと段階的に治療を続けることになります。
一般不妊治療はどのような流れで行われるのかを知っておくと、初めての不妊治療でも落ち着いて対応できるでしょう。
ここでは、タイミング法と人工授精の治療の流れについて解説します。
タイミング法
タイミング法は排卵日を特定し、医師が性交のタイミングを指導して自然妊娠に繋げる方法です。
タイミング法の流れ(月経周期が28日の場合)は以下のようになります。
- 排卵日を推定する
- 排卵誘発剤の使用を検討する(月経開始~5日目ごろ)
- 月経周期や超音波検査、排卵検査キットなどを用いて正確な排卵日を予測する(月経開始から12~14日目ごろ)
- 医師が指導したタイミングで性交を行う
- 妊娠判定検査を行う
タイミング法を3~6回続けても妊娠に繋がらない場合には、人工授精へと移行するのが一般的です。
人工授精
人工授精は、培養液で洗浄した精子を細い管を使用して子宮の奥まで入れることで受精、着床の可能性を高める方法です。
人工授精の治療の流れ(月経周期が28日の場合)は以下のようになります。
- 超音波検査などで排卵日を予測する(月経開始後10~12日目ごろ)
- 病院か自宅で精液を採取する(月経開始後10~12日目ごろ)
- 精液を培養液で洗浄・濃縮する
- 精子を子宮の奥に注入する(月経開始後12~14日目ごろ)
- 妊娠判定検査を行う
人工授精の場合、排卵誘発剤を使用する可能性があることに注意が必要です。
排卵誘発剤の使用は、卵胞の育ち具合や人工授精を繰り返しても妊娠に至らない場合に検討され、月経開始直後から使用するかを決定します。
生殖補助医療へのステップアップの時期は女性の年齢にも左右されますが、人工授精を行ってから3~6ヵ月経過しても妊娠に至らなかった場合に検討されることが一般的でしょう。
生殖補助医療(ART)
人工授精で妊娠に繋がらなかった場合には、体外受精や顕微授精などの治療がある生殖補助医療(ART)に移行します。
ARTの中で不妊治療によく検討されるのは体外受精と顕微授精です。
体外受精と顕微授精がどのように行われるのかについて、以下で詳しく見ていきましょう。
体外受精・顕微授精
体外受精・顕微授精は、手術により卵子を採取し、体外で精子と受精させた後に子宮へ戻す方法です。
体外受精はシャーレ上で精子を卵子に振りかけて自然に受精させる方法に対し、顕微授精は顕微鏡を見ながら、精子1個を細いガラス管を使って卵子に注入し受精させる方法です。
一般的に、体外受精で妊娠に至らなかった場合のステップアップとして、顕微授精が検討されます。
ここでは、体外受精・顕微授精の治療の流れを解説します。
- 月経周期に合わせて排卵をコントロールするための投薬を開始する
- 卵子を複数育てるため卵巣を刺激する(月経開始後3日目ごろ)
- 採卵・採精(月経開始後12~18日目ごろ)
- 受精
- 受精卵が胚になるまで培養する(最長6日間)
- 胚を子宮の中に移植する
- 妊娠判定検査をする
卵巣刺激方法(排卵誘発方法)には、完全自然排卵周期法、低刺激法、中刺激法、高刺激法などがありますが、どの方法を適用するかは、希望や個人の状態を見ながら医師が判断します。
不妊治療に初めて行くタイミングは?

「不妊治療っていつから始めればいいの?」「初めて行くタイミングがわからない」などの悩みを持っている方も少なくありません。
結論から言うと、不妊治療に行くタイミングは明確に決まってはいませんが、タイミングをはかっても妊娠できないことが続き、「不妊かもしれない」と思った時が受診のタイミングです。
不妊治療は不妊の原因や年齢などによっても個人差がありますが、長い治療期間になることも少なくないため、早めの治療開始が推奨されます。
また、不妊治療の保険適用に関しては、体外受精や顕微授精などの生殖補助医療の適用に43歳未満という条件がついていますし、年齢によって保険適用になる胚移植の回数が異なります。
不妊かもしれないと思ったら、早めに専門家である医師に相談することをおすすめします。
不妊治療を検討する人が気になる疑問

不妊治療を検討しているけれど、わからないことが多く受診をためらっているという方もいるかもしれません。
ここでは、不妊治療を受ける前に知っておきたい疑問について回答します。
Q:初診時の持ち物や準備しておくものはある?
クリニックを問わず、不妊治療の初診時に必ず必要なものは健康保険証です。
夫婦で受診する場合には、夫婦それぞれの保険証が必要になりますので準備しておきましょう。
クリニックによって必要になる可能性のあるものは以下のとおりです。
- 顔写真付き公的身分証
- 住民票・戸籍謄本
- 基礎体温表
- 他院で検査した1年以内の血液検査のデータ
- 問診表
- 紹介状
不妊治療をするにあたって公的身分証が必要な理由は、治療を受ける方の本人確認や、法的な親子関係を明確にするためです。
公的身分証明として認められる書類はクリニックによって異なるため、事前に確認しておきましょう。
住民票や戸籍謄本は、不妊治療を受ける方が婚姻関係にあるかを確認するために必要です。
初診時にどの書類が必要かはクリニックによって異なるため、受診する際に確認しておくことが大切です。
Q:不妊治療の初診の時は何て言えばいい?
不妊治療の初診の際、何て言えばいいのかわからないと悩む方も少なくありません。
初診の申し込み時は、妊娠を希望していること、不妊治療を考えていることを伝えましょう。
初診時に聞かれる内容については上述していますので、そちらを参考にしてください。
また、気になることがあるけれど口に出しにくいと言った場合には、問診表に記載すれば医師にも伝えることができます。
Q:生理中に受診してもいい?
不妊治療を検討していても、初診で受診しようとした日に生理になってしまったというケースもあるかもしれません。
経腟超音波検査については、生理中に行わないクリニックもありますが、そのほかの採血などの検査は行うことができます。
不妊治療は、できるだけ早く行うことが重要ですので、生理中であってもまずは受診し医師と相談しましょう。
不安な場合は、受診前に電話でクリニックに相談するのもおすすめです。
Q:夫婦で受診するべき?
不妊治療を夫婦で受診すべきかは、ルールとして定められておらず、クリニックによって異なります。
しかし、初診時は夫婦そろって受診することがおすすめです。
理由は以下のとおりです。
- 男性の検査を初診時にすませることで治療がスムーズにすすむ
- 医師からの説明を夫婦そろって聞くことで双方の理解と治療への希望がわかりやすくなる
- 夫婦間の不妊治療のギャップを少なくできる
女性一人で受診するケースであっても、不妊治療は夫婦の話し合いと希望のすり合わせが重要です。
不妊治療を夫婦で協力しあって進めていくことで、精神的な負担軽減やモチベーションの上昇にも繋がります。
Q:不妊治療の通院頻度は?
不妊治療の通院頻度は、治療方法によって異なります。
月経周期を28日とした場合の通院頻度は平均して、一般不妊治療の場合は1~2時間の通院を月に2~6回、生殖補助医療の場合は1~3時間の通院を月4~10回に加え、半日~1日の通院が月1~2日必要です。
仕事との両立を不安に思う方もいるかもしれませんが、不妊治療が保険適用になったことで、会社にも通院を伝えやすいかもしれません。
不妊治療と仕事と両立させるための方法について詳しく記載されている記事がありますので、参考にしてみてください。
→不妊治療の通院頻度はどれくらい?治療の流れや仕事と両立させるための方法を解説
Q:不妊治療は痛い?
不妊治療というと痛いイメージをお持ちの方もいるかもしれません。
痛みの感じ方には個人差がありますが、主に以下のような検査の際に痛みを感じる可能性があります。
- 経腟超音波検査
- 採血
- 薬剤の注射
- 子宮卵管造影でのチューブ挿入
採卵の際には麻酔を使うことが一般的ですので、痛みを感じることはほぼありません。
痛みが不安な方は事前にクリニックの医師やスタッフに相談しましょう。
心配なことや不安になっていることを話し、対処できるものはしてもらうことで不安感を解消することが大切です。
Q:不妊治療の期間はどのくらい?
不妊治療の期間は人によって個人差が大きく、3ヵ月以内で妊娠する場合もあれば2年以上かかる場合もありますが、平均して2年程度と言われています。
妊娠するまでの期間は年齢、不妊の原因などによりさまざまです。
長い期間を治療に費やす場合もありますので、夫婦間でモチベーションを保ちつつ、信頼できるクリニックで不安や精神的な負担を解消することが大切です。
まとめ
不妊治療の流れは、初診での問診や基本検査で不妊の原因を調べ、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精とステップアップしていくのが一般的です。
不妊治療について不安になる方もいるかもしれませんが、信頼できるクリニックを受診することで、不安や精神的な負担を軽減しながら治療を行っていくことが大切です。
『三軒茶屋ウィメンズクリニック』では、一人ひとりの患者さんに対し親切丁寧に向き合い、オーダーメイドの治療を提案してまいります。
はじめての不妊治療で不安な方にも、安心して受診していただけるよう、徹底したプライバシーの保護や心に寄り添った医療体制を心がけております。患者さんの疑問や不安を解消するため、妊活の基礎知識を説明する『妊活セミナー』や『体外受精説明会』なども開催していますので、ぜひご参加ください。
